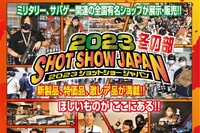田村装備開発 大阪出張訓練「野戦」1日目(座学)レポート

注意:
公開情報をベースとしているものの、講座の性質上、一部にセンシティブであると思われる情報を含んでいる。それらについては筆者の判断で伏せている。
田村装備開発公式ブログ
http://tamura.militaryblog.jp/
■すべての戦いにはルールがある
田村装備開発の講座は毎回「戦闘におけるルール」からスタートする。
田村装備開発訓練教育部の長田部長。元陸上自衛隊SOG所属という野戦のスペシャリストである。

戦闘というものは、一見混沌としたものだが、実際には有形無形の縛りが存在している。
例えば自分の身に危険が迫っていても「正当防衛」を超える実力行使は罪に問われるし、犯罪者を取り締まる警察官は警職法、自衛官は自衛隊法にその行動が規定される。仮に国外での活動を行うとすれば、国際間の条例や条約の対象となる。「達成したい目標」「避けたい結末」など明文化されていない縛りも存在する。
野戦は国際関係の一部であり、様々なレベルのレギュレーションが絡んでいる。その実行にあっては自分の戦いが何を達成するものか、より戦略的・政治的な視座をもって考える必要がある。
レギュレーションをどう捉え、何を指針とするかに明快な答はない。座学では度々ディスカッションが挟まれ、各人に思考を促していた。

軍事的知識だけでなく、様々なことに関心をもつことが重要であると語る長田氏。直近の事件を追いかけるだけでなく戦史や政治状況、関連科学技術などに目を向け、意識においておく必要があるという。

■戦いのプランニング
上位者から命令を受領すれば、実行部隊は作戦計画とその実行について考えることになる。国ごとに様々な雛形が存在するが、特殊作戦では以下の項目を用いて検討を行うという。
「任務目標」と「エンドステート」は似ているが非なるものだ。例えば「人質の救出」という任務があった場合「あらゆる犠牲をはらって突入する」のか「負傷者ゼロで救出を達成する」のか、達成後のイメージを含めて考えるのがエンドステートである。
IPBで人質の負傷が確認されれば時間的な制限が発生するであろうし、人質が外国の政治家などであれば外交上の影響を考慮にいれる必要があるだろう。こうして任務の目標はIPBを通じて再定義されエンドステートとなる。実行すべきキータスクはエンドステートから逆算されるから、IPBがあらゆる情報をカバーしていなければエンドステートの精度は落ち、リスクは高まっていく。
このプロセスは作戦ないし部隊の性質や規模によって変化する。興味のある方は「Military Decision-Making Process(MDMP……軍事的意思決定プロセス)」を扱う論文、フィールドマニュアル等を参照されたい。
■諸元の理解と戦技の実行
タスクが明らかになれば、最後は戦場で戦技を実行しこれを達成することになる。CQBと野戦では行動単位や戦技が異なるとする考えがある一方、田村装備開発では一定の条件下では近しいものとしているようだ。
銃の射程、命中精度から弾丸の到達時刻を考察する。光学機器の発展により物理的距離の長短は次第に無視できるようになっており、今後、CQBと同様の速度域で戦闘が展開する可能性があるという

これは、人間の反応速度や銃の性能、平均的な体力といった一定した数値、諸元から導かれる。田村装備開発では「人間の反応速度0.3秒」をベースにした戦技の組み立てを行うことが多いようだ。これに弾速や命中精度などを加味した場合、一般的な野戦における有効戦闘射程3~400メートルでは、敵に視認された場合最速で0.6秒以内にこちらに着弾する。こうした速度域では声や手信号で意志の疎通を図りながらの行動は、CQBの時と同様に間に合わない。この点で、CQBも野戦も各個での1vs1の戦闘がベースになる。
もちろん、交戦距離がまったく違う以上、敵の見え方や射撃の要領は違うものになる。地形の高低差も大きく、より立体的な運動を考える必要があるだろう。CQBでは隊列の先頭にいるポイントマンが重要な役割を果たすが、野戦で横隊を組んだ場合、誰が「ポイントマン」になるのかなど、独特なコンセプトもある。
次稿では戦技訓練で紹介された様々なテクニックについて取り上げる。
(続く)
Photo & Text: Chaka (@dna_chaka)
田村装備開発の講座は毎回「戦闘におけるルール」からスタートする。
田村装備開発訓練教育部の長田部長。元陸上自衛隊SOG所属という野戦のスペシャリストである。

戦闘というものは、一見混沌としたものだが、実際には有形無形の縛りが存在している。
例えば自分の身に危険が迫っていても「正当防衛」を超える実力行使は罪に問われるし、犯罪者を取り締まる警察官は警職法、自衛官は自衛隊法にその行動が規定される。仮に国外での活動を行うとすれば、国際間の条例や条約の対象となる。「達成したい目標」「避けたい結末」など明文化されていない縛りも存在する。
野戦は国際関係の一部であり、様々なレベルのレギュレーションが絡んでいる。その実行にあっては自分の戦いが何を達成するものか、より戦略的・政治的な視座をもって考える必要がある。
レギュレーションをどう捉え、何を指針とするかに明快な答はない。座学では度々ディスカッションが挟まれ、各人に思考を促していた。

軍事的知識だけでなく、様々なことに関心をもつことが重要であると語る長田氏。直近の事件を追いかけるだけでなく戦史や政治状況、関連科学技術などに目を向け、意識においておく必要があるという。

■戦いのプランニング
上位者から命令を受領すれば、実行部隊は作戦計画とその実行について考えることになる。国ごとに様々な雛形が存在するが、特殊作戦では以下の項目を用いて検討を行うという。
・任務
・地位
……作戦上の位置づけと役割
・IPB(Intelligence Preparation of the Battlespace……戦場情報準備)
……戦場を取り巻く物理的環境、地形、気象
……政治的環境
……敵の能力(E/C)、配置、とられる可能性のある行動(probability of COA)、高価値目標(HVT)
……その他あらゆる周辺情報
・エンドステート
……IPBを元に再定義された任務目標。最も望ましい作戦終了後の状況のイメージ
・キータスク
……エンドステートから時系列を逆算させて得られる、必ず達成されなければならないタスク
・リスクコントロール
……各キータスクにおける不確定要素の洗い出し
・ダメージリカバリー
……リスクとして洗い出せなかった予想外の自体への対処
・任務中止の要件決定
……実行部隊に中止を判断させるための要件
「任務目標」と「エンドステート」は似ているが非なるものだ。例えば「人質の救出」という任務があった場合「あらゆる犠牲をはらって突入する」のか「負傷者ゼロで救出を達成する」のか、達成後のイメージを含めて考えるのがエンドステートである。
IPBで人質の負傷が確認されれば時間的な制限が発生するであろうし、人質が外国の政治家などであれば外交上の影響を考慮にいれる必要があるだろう。こうして任務の目標はIPBを通じて再定義されエンドステートとなる。実行すべきキータスクはエンドステートから逆算されるから、IPBがあらゆる情報をカバーしていなければエンドステートの精度は落ち、リスクは高まっていく。
このプロセスは作戦ないし部隊の性質や規模によって変化する。興味のある方は「Military Decision-Making Process(MDMP……軍事的意思決定プロセス)」を扱う論文、フィールドマニュアル等を参照されたい。
■諸元の理解と戦技の実行
タスクが明らかになれば、最後は戦場で戦技を実行しこれを達成することになる。CQBと野戦では行動単位や戦技が異なるとする考えがある一方、田村装備開発では一定の条件下では近しいものとしているようだ。
銃の射程、命中精度から弾丸の到達時刻を考察する。光学機器の発展により物理的距離の長短は次第に無視できるようになっており、今後、CQBと同様の速度域で戦闘が展開する可能性があるという

これは、人間の反応速度や銃の性能、平均的な体力といった一定した数値、諸元から導かれる。田村装備開発では「人間の反応速度0.3秒」をベースにした戦技の組み立てを行うことが多いようだ。これに弾速や命中精度などを加味した場合、一般的な野戦における有効戦闘射程3~400メートルでは、敵に視認された場合最速で0.6秒以内にこちらに着弾する。こうした速度域では声や手信号で意志の疎通を図りながらの行動は、CQBの時と同様に間に合わない。この点で、CQBも野戦も各個での1vs1の戦闘がベースになる。
もちろん、交戦距離がまったく違う以上、敵の見え方や射撃の要領は違うものになる。地形の高低差も大きく、より立体的な運動を考える必要があるだろう。CQBでは隊列の先頭にいるポイントマンが重要な役割を果たすが、野戦で横隊を組んだ場合、誰が「ポイントマン」になるのかなど、独特なコンセプトもある。
次稿では戦技訓練で紹介された様々なテクニックについて取り上げる。
(続く)
田村装備開発公式ブログ
http://tamura.militaryblog.jp/
Photo & Text: Chaka (@dna_chaka)
Chaka (@dna_chaka)
世界の様々な出来事を追いかけるニュースサイト「Daily News Agency」の編集長。
★この記事へのコメント
コメントを投稿する
★この記事をブックマーク/共有する
★新着情報をメールでチェック!
★Facebookでのコメント